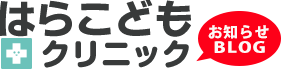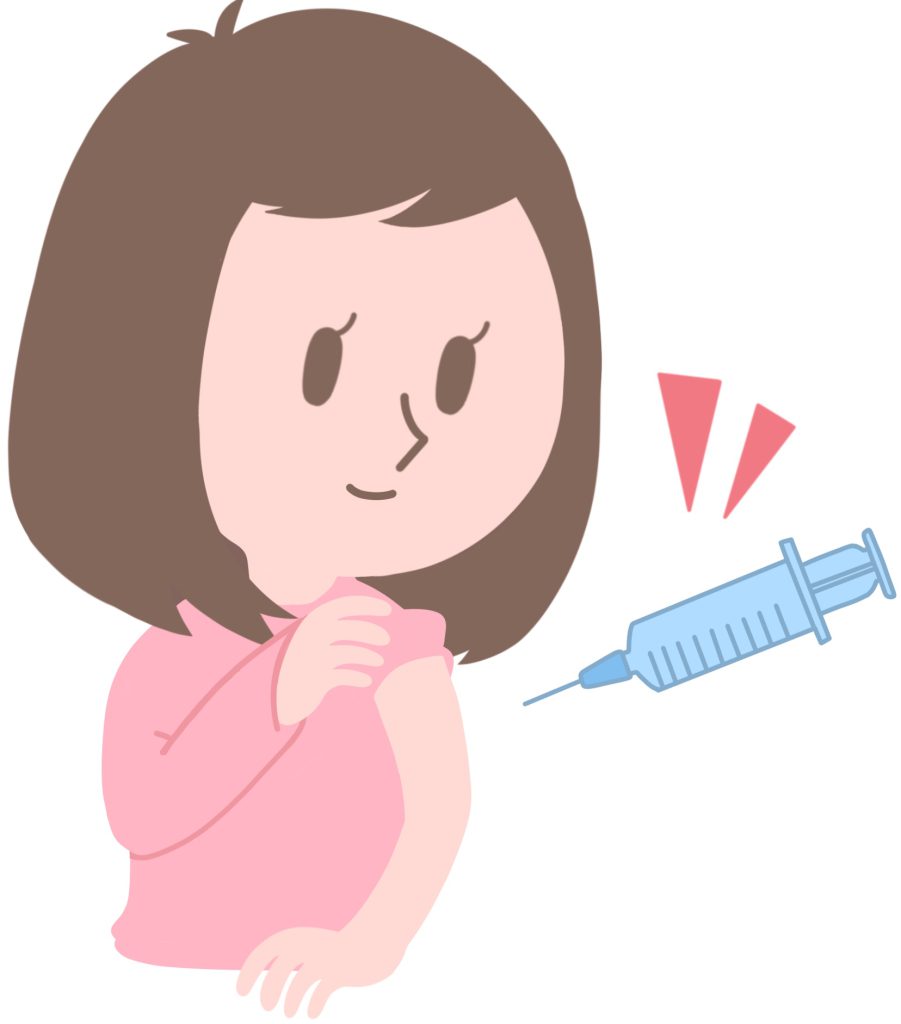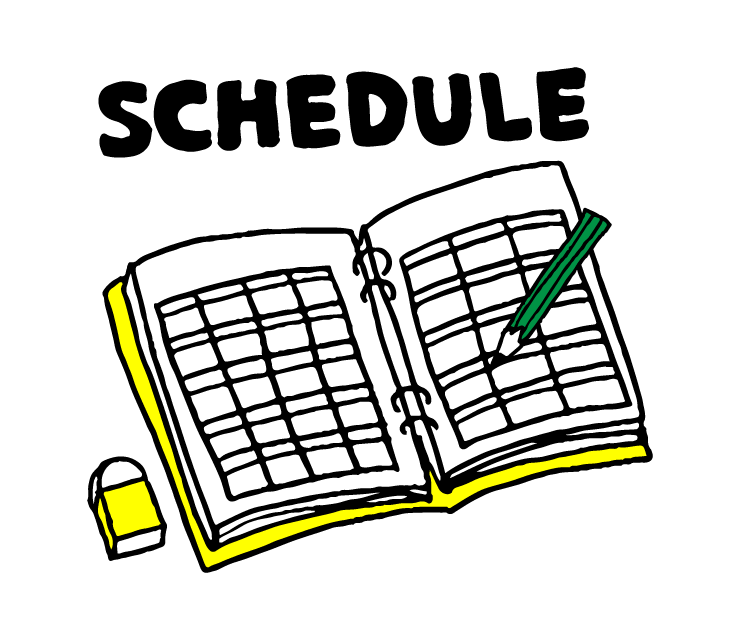
2023年4月から、お子さんのワクチンスケジュールについて、いくつか変更がありました。
1.四種混合ワクチンの接種開始生後3カ月→生後2カ月
これまで生後3カ月の接種開始だった四種混合ワクチンが、2カ月での接種開始となりました。
これは四種混合ワクチンで予防できる病気(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)のうち、百日咳について、ワクチン未接種の場合、重症化し死亡するケースがあるのではないかという疑いがあったため、接種の時期を早めたという経緯です。
2カ月から接種できるほかのワクチン「ヒブ」・「小児用肺炎球菌」・「ロタ」・「B型肝炎」と合わせ、5つのワクチンを同時接種するのがおすすめです。はらこどもクリニックでワクチンデビューするほとんどのお子さんが、同時接種を選択しています。
ロタワクチンは飲むタイプのワクチンなので、左右の上腕に2本ずつという形になります。
2.HPVワクチン4価→9価へ
4月からこれまで4価だったHPVワクチンが9価ワクチンへ変更となります。4価は3回接種でしたが、9価は15歳未満は2回接種、15歳以上は3回接種となります。HPVワクチンは全額助成が出る定期接種になりますので、接種対象年齢(小学校6年生~高校1年生に相当する女子)の方は、自己負担なしでの接種になります。
また本来接種するはずだった時期に、国が積極的な勧奨を控えており、接種することができなかった世代の方(誕生日が1997年4月2日~2007年4月1日)についても、公費負担でキャッチアップ接種が可能です。こちらも9価での接種が可能ですので、是非接種をお願いします。
所沢市の小児科・内科・アレルギー科・糖尿病内科 はらこどもクリニック
〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町2-1379