
スギ花粉の免疫療法につきまして、ヒノキ花粉のシーズンが終わる6月から新規の治療を開始したいと思います。(免疫療法の詳細については、こちらの記事をご覧ください)
免疫療法には、定期的に通院して注射を行う皮下免疫療法と、患者さんご自身で毎日1回薬を服用する舌下免疫療法がありますが、基本的には舌下免疫療法で治療を行っています。
舌下免疫療法の治療の流れについてご説明すると
①まず最初に採血をし、アレルギー検査を行います。
②初回の薬の服用については、アナフィラキシーの可能性がありますので、必ず来院していただき服用します。服用後、問題が無いかどうか院内で30分程度待機していただきます。
③2回目についても薬の量を増やしますので、来院して薬を服用していただきます。
④最初のうちは、様子を見ながら薬の濃度を調整していきます。この期間につきましては、必要に応じて何度か来院していただくことになります。
⑤その後は決められた量の薬を1日1回患者さんご自身で服用してていただきます。特に問題が無いようであれば、長期分(1カ月~2カ月分)の薬を処方いたします。
舌下免疫療法の治療期間は最低でも3年、基本は5年と言われています。(治療の状況によってはさらに伸びる場合もあります。)2年で止めてしまうと、3年目に元に戻ってしまう例が多く報告されています。1日1回薬を服用するというのは簡単なようで意外と忘れがちで、面倒になって服用を止めてしまうというケースも少なくありません。
薬を服用する時間については特に指定は無いのですが、服用後5分間は、飲食やうがいはしないでください。また服用の2時間前~2時間後の間は、激しい運動と入浴は避けるようにしてください。
飲酒の習慣がある場合、アルコールとの併用はいけませんので、お酒を飲む時間の前後を避け、朝に服用するなどしてください。
治療期間が長期に渡るとはいえ、効果自体はもっと早く出ることが多いです。例えば今年の6月から治療を始めた場合は、来年の花粉シーズンにはある程度の効果が期待できるでしょう。
舌下免疫療法については公的な健康保険が効きます。15歳未満の場合、医療費の助成がありますので、自己負担なしで治療できます。
ちなみにはらこどもクリニックでは、スギだけではなくダニの免疫療法も行っています。ダニをやっている医療機関は埼玉県内でもほとんどありません。免疫療法は、辛いアレルギー症状を抑えられる数少ない治療法です。免疫療法をご希望の方はお気軽にご相談ください。
所沢市の小児科・内科・アレルギー科・糖尿病内科 はらこどもクリニック
〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町2-1379
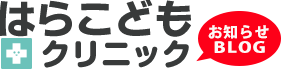
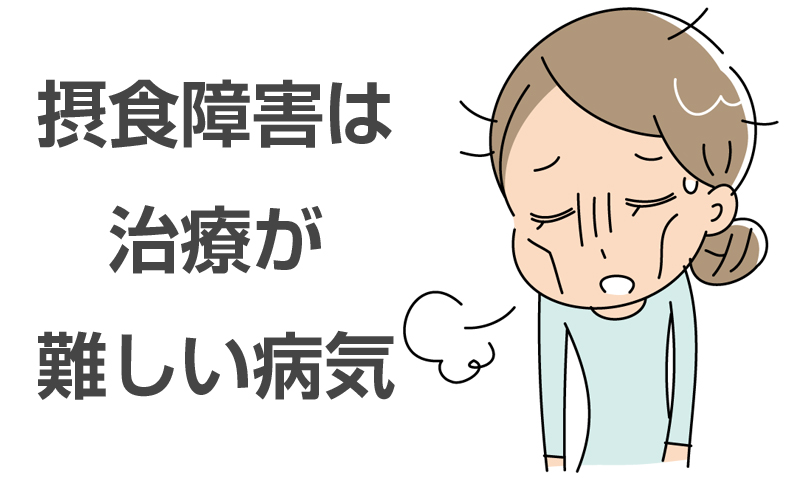


 少しずつですが、医療関係者のへの新型コロナウイルスワクチンの接種が進み、高齢者の方への接種スケジュールを公表する自治体も出てきました。このブログをお読みのみなさんも、テレビや新聞などで、予防接種の写真を目にしたことと思います。
少しずつですが、医療関係者のへの新型コロナウイルスワクチンの接種が進み、高齢者の方への接種スケジュールを公表する自治体も出てきました。このブログをお読みのみなさんも、テレビや新聞などで、予防接種の写真を目にしたことと思います。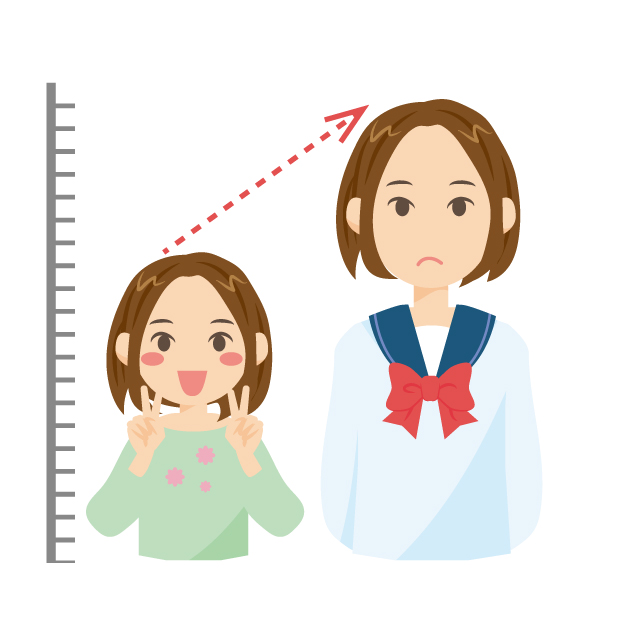


 ワクチン接種の副反応としてアナフィラキシーがあります。
ワクチン接種の副反応としてアナフィラキシーがあります。