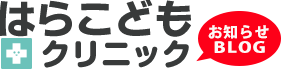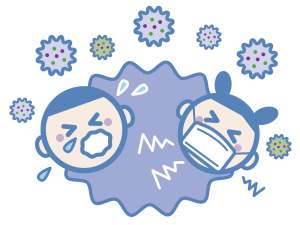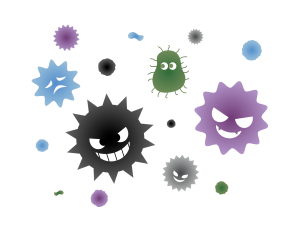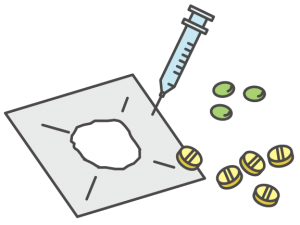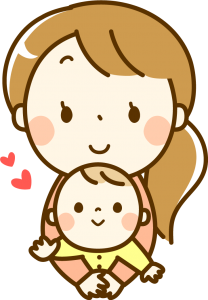
小さなお子さんが健やかに育っているかを確認し、子育てについての様々な悩みを相談できるのが乳幼児健診です。所沢市では、国によって定められた4ヶ月、1歳6ヶ月、3歳の3回は、基本的に保健センターでの集団健診となり、10ヶ月健診は医療機関で行うようになっています。(乳幼児健診の実施時期や実施場所は、自治体によって異なりますので、所沢市以外の方は、「乳幼児健診 自治体名」で調べてみましょう。)
乳幼児健診はとても大切です。乳幼児健診をしっかりとできるかによって、お子さんの「運命が変わる」こともあるのです。お子さんが今現在病気に罹っていないかはもちろん、生まれつきの疾患などを持っていないか、発育・発達に異常がないかなどを調べていきます。そこで何らかの病気が見つかることもありますし、身長や体重が成長曲線から外れていないかなども調べてもらえます。
あるお子さんの例では、健診で身長の伸びが悪いということがわかり、その後は専門医によって成長ホルモンが正常に出ているかの検査を行い、大きくなった現在では、身長について定期的に検査し、低身長の治療を行っているというケースもあります。
先ほど書いたように所沢市では基本的に4回健診があるわけですが、本来はこの4回以外にも成育のハブとなる時期にはやったほうが良いのです。特に行政のシステムの中に乳幼児健診が組み込まれている中では、健診の連続性が保てなかったり、健診後のフォローなどがやりきれず、健診さえできればOKという状態になってしまうこともあるからです。
親御さんがお子さんを見てちょっと様子がおかしいな?とか、ちゃんと育っているのかな?など不安になってしまった時に、乳幼児健診を行って、きちんと医師に診てもらい不安を解消することは、子育てにおいてとても有意義なことです。ですので、気になることがあったら、いつでもお気軽に乳幼児健診の相談をしてください。
ちなみに乳幼児健診については、医師の側でも課題になっています。健診においてしっかりと子供を診るには、様々なポイントがあり、若手の医師に対しては、本来はきちんとした教育が必要なのです。しかし、乳幼児健診の正しいやり方というのは体系化されているとは言えず、若い医師たちが経験を積みにくい分野でもあるのです。
そういった問題を少しでも解決しようと、原院長は医療誌に若手医師やコメディカル(医師以外の医療従事者)向けに「乳幼児健診のコツ」を編集・寄稿したり、乳幼児健診の効果的なやり方をまとめた書籍を出版するなどの活動を行っています。(※書籍については、まだ出版前ですので、出版時期が明確になりましたら、またブログにてお知らせいたします。)
〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町2-1379
診療時間 午前 8:40〜12:00 午後 15:00〜18:00
受付時間 平日 8:30〜18:00 土曜日 8:30〜12:00
休診日 日曜日 祝日 (年末年始 お盆休みあり)