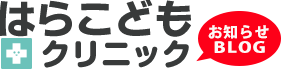食材による口腔内のアレルギー反応を「口腔アレルギー症候群」と言います。口の周りがピリピリしたり、喉の奥がイガイガしたりといった症状が現れます。その中でも、花粉との交差反応により起こるアレルギー症状を「花粉-食物アレルギー症候群=pollen-food allergy syndrome(PFAS)」と呼ぶようになりました。
少し前に大田区の小学校でビワを食べた子どもたち11人がアレルギー症状で救急搬送されるというニュースがありました。これはPFASが原因と思われ、花粉によるアレルギーが、他の植物に対するアレルギーを引き起こした分かりやすい例でしょう。
日本における花粉症のほとんどは「スギ花粉」が原因です。しかしこのスギ花粉に対するアレルギー反応が、徐々にハンノキやシラカバに対しても広がっていくケースがあります。さらにこのハンノキへの反応が、バラ科の植物への反応に広がっていきます。バラ科には食用にされる果物が多いため(ビワ、モモ、リンゴ、サクランボ、イチゴなど)、普段の何気ない食生活で、急にアレルギー反応を引き起こしてしまうケースが出てくるのです。
なぜこんなことが起こるのでしょうか。植物が感染防御のために持っているタンパク質(PR-10)があります。花粉とバラ科でこのPR-10の構造が似ているため、交差反応が起こってしまうのです。
最近では、スギ花粉から他の植物へアレルギー反応が広がるケースが本当に多くなっています。小さいお子さん、2歳くらいでもハンノキ、シラカバへの反応が見られる患者さんも少なくありません。症状としては軽い方が多いのですが、ごくまれにアナフィラキシーを起こす方もいます。スギへの反応が高い方に起こりやすいので、花粉症自体も症状が重い方が多いです。
PFASを防ぐ治療のひとつが「免疫療法」です。他のアレルギーが起こる前、早めにスギに対する免疫療法を行うと、他の植物に対する交差を抑えることができると言われています。免疫療法は花粉の時期には始められませんので、もし「PFASかも?」という方は、きちんと検査をして今のうちに免疫療法を検討するのも良いかもしれませんね。
所沢市の小児科・内科・アレルギー科・糖尿病内科 はらこどもクリニック
〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町2-1379
診療時間 午前 8:40〜12:00 午後 15:00〜18:00
受付時間 平日 8:30〜18:00 土曜日 8:30〜12:00
休診日 日曜日 祝日 (年末年始 お盆休みあり)